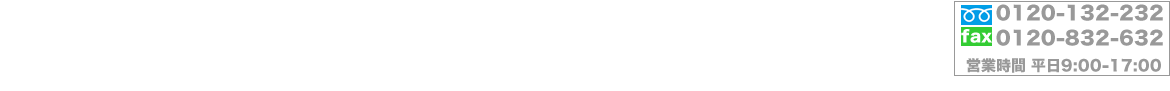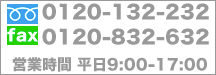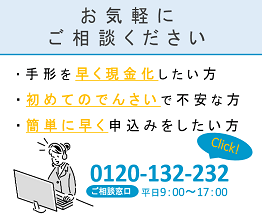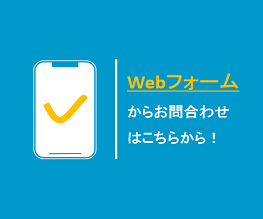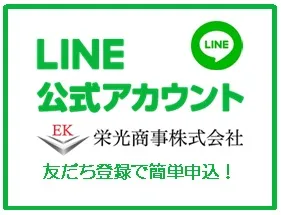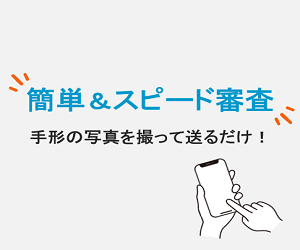手形割引の手数料とは?
手形割引の手数料には、割引料・取立料・その他費用の3つの費用があります。
- 手形割引の割引料は、以下の式のように手形の額面金額に残存日数と割引率をかけ、日割り計算で算出されます。
- 取立料は手形の額面に関係なく1枚当たりにかかる費用です。
- その他費用には、契約時の印紙代、振り込みでの取引時には振込料がかかります。
- 割引率の目安
- さらに、個人事業者様を対象に(コロナに負けるな!応援特別企画実施中)を実施しております。こちらも、是非ご覧ください。
- シミュレーター
割引料=手形額面金額×割引日数×割引率(%)÷365(閏年の場合は366日)
割引率(%)は手形の振出人(手形を発行する企業)の信用度や額面、残存日数など、いろいろな要因によって定められます。
銀行など金融機関では、振出人による割引率の変動幅は小さく、割引業者ではその変動幅は大きくなる傾向があります。
銀行では手形割引は振出人の信用度ではなく、持込人(申込者)の信用度によって割引するのに対して、割引業者は持込人より振出人の信用度で
割引することが多いからと思われます。残存日数は手形割引の実行日から支払期日までの日数に現金化に必要な取立日数を加算されます。
取立料は手形1枚につきいくらと各金融機関によって決められています。手形割引か取立か、また地方交換や取立に出すタイミングによっても手数料が異なります。 金融機関の取立料は1枚につき220円から1,320円です。弊社の取立料は1枚につき、660円となっていますが、初回お取引の場合は無料サービス0円となっております。
割引業者の中には調査料や事務手数料、諸費用などの項目で手数料を徴収する場合があります。弊社では割引料と取立料、振込時には振込料がかかりますが、 そのほかの手数料は一切いただきません。また、初回取引時には振込料や取立料が無料サービス0円となる特典もありますので、 こちらから詳細はご覧ください。
手形の割引が認められているのは銀行などの金融機関と貸金業登録をしている会社だけです。
そのため、手形割引の上限の割引率は年率20%となります。(割引料や取立料や手数料が天引きされた実質金利で年率20%以内。)
現在の割引率は銀行だと高くても2%台、信用金庫や信用組合は銀行に比べると割引率が高い場合があるようですので、3%より高いようであれば、
金融機関へ金利引き下げの交渉をすることをお勧めします。最近の割引業者では、表面金利は2%台後半から高くても18%程度です。
額面に対して1ヶ月、1%で年率12%、額面の0.5%で年率6%です。額面100万円、期日まで3ヶ月の手形だと1万円〜3万円程度、
上限金利だとしても5万円にはなりません。残存日数によって異なりますが、割引料を考慮して見積もりを出す場合などは、単純に支払期日までの期間が1ヶ月ごとに
額面の0.5%や1%と計算すればわかりやすく計算できるでしょう。(例:残存期間3ヶ月で手形額面の1.5%〜3.0%が割引料)
弊社の割引率の目安はこちら↓をご覧ください。
さらに、もう少し細かく計算してみたいという方の為にシミュレーターでご確認ください。 額面や残存日数、割引率をいろいろと組み合わせて、割引料が確認できます。